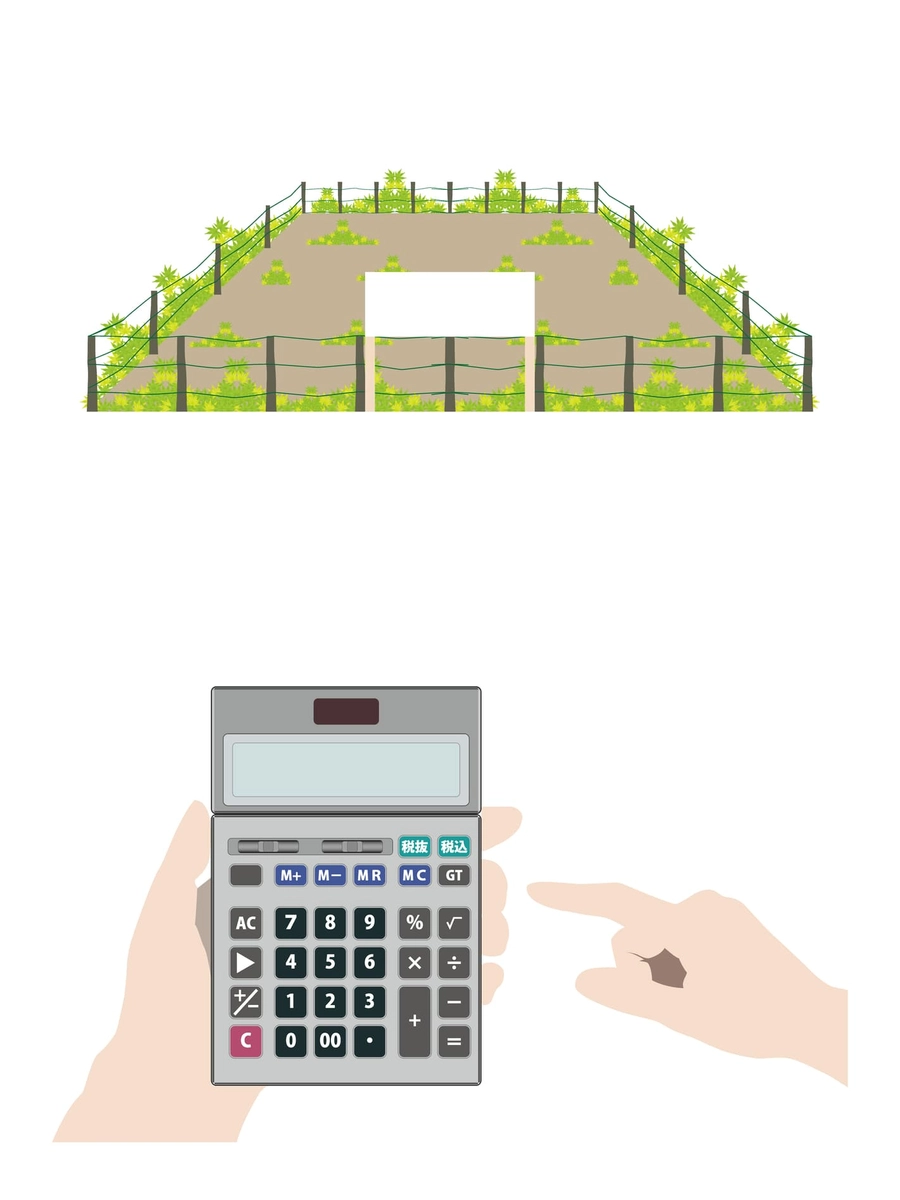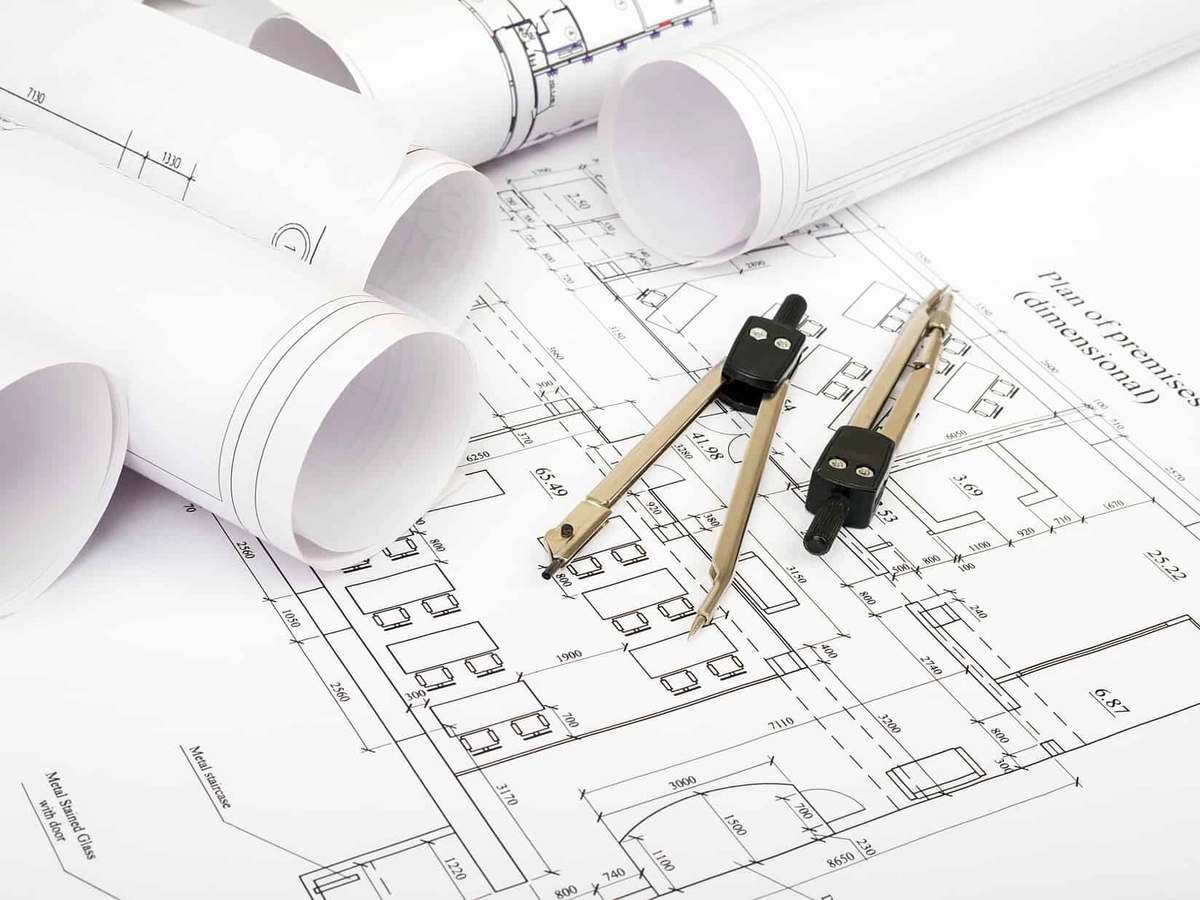土地には建築制限がある
 写真②建ぺい率と容積率 (1).jpg 47.56 KB
写真②建ぺい率と容積率 (1).jpg 47.56 KBマイホーム用に土地を購入しても「大きさや高さなどすべて自由な住宅を建てられる」というわけではありません。それぞれの土地には建築制限があり、どのような規模の家を建てられるか決まっているのです。主な建築制限をチェックしてみましょう。
【建築制限の例】
・建ぺい率
・容積率
・絶対高さ制限
・日影制限 など
立地や利便性も重要ですが、土地の建築制限を確認して理想のマイホームが叶うかどうか検討する必要があります。さまざまある建築制限の中でも、今回は「建ぺい率」と「容積率」に着目していきましょう。
建ぺい率の基礎知識
建ぺい率とは、土地の敷地面積に対して建築面積が占める割合です。建築面積に該当するのは、建物を真上から見たときの範囲です。例えば、2階より1階の方が広い住宅の場合、1階の部分が建築面積になります。
土地ごとに建ぺい率が何%であるか決まっており、その範囲内に建築面積を収める必要があります。
建ぺい率が設けられている理由
敷地面積ギリギリまでの家が立ち並ぶ住宅街をイメージしてみてください。住宅が密集しすぎて景観が美しくないばかりか、風通しや日当たりが充分に確保できません。さらに、火災が起こったら隣家に延焼しやすいリスクも。このような事態を防ぎ、住民が生活しやすいように規制が設けられているのです。
建築面積に含まれるもの・含まれないもの
以前の建築基準法では、建築物より1m以上突出しているバルコニーやひさしは建築面積にカウントされていました。しかし、2023年4月1日に改正され、現在は突出部分が5mまで不算入となっています。また、屋根がない駐車場や中庭も建築面積に入りません。
ただし、バルコニーの両サイドに壁があったり、屋根がついていたりすると建築面積に含まれます。屋根つきの駐車場なども同様です。
参考元:国土交通省「運用改善政令」
建ぺい率の計算式
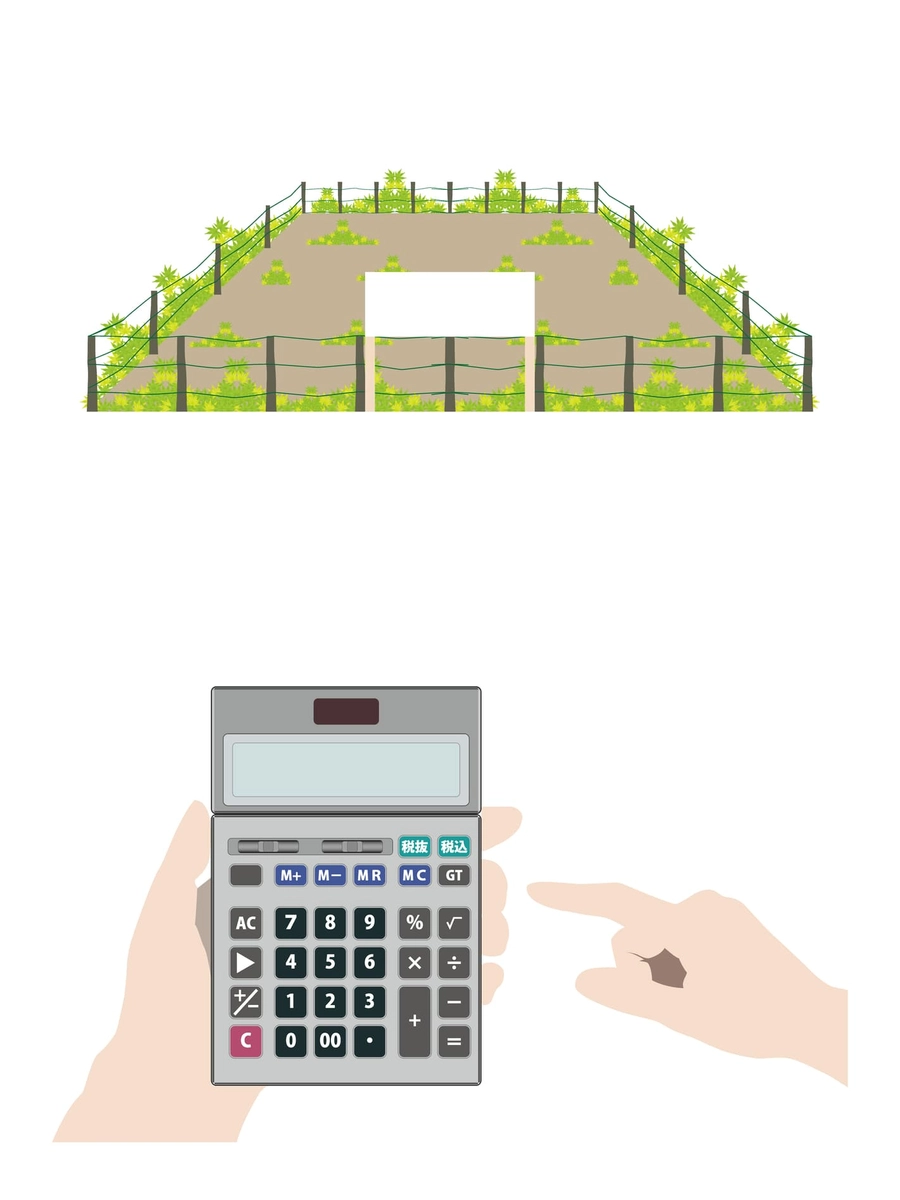 写真③空地と電卓 (1).jpg 91.14 KB
写真③空地と電卓 (1).jpg 91.14 KB建ぺい率は、以下の計算式で求めます。
【建築面積÷敷地面積×100=建ぺい率(%)】
50坪の土地に建築面積20坪の住宅を建てる場合、建ぺい率は40%となります。
参考元:国土交通省「建築基準法制度概要集」
建ぺい率の特例
建ぺい率には特例があり、要件を満たすと制限が緩和されます。一般住宅の場合、おもに次の緩和が認められます。
| 要件 |
緩和内容 |
| 防火地域内に耐火住宅を建てる場合(A) |
10%緩和 |
| 特定行政庁指定の角地に住宅を建てる場合(B) |
10%緩和 |
| A・B両方に該当する場合 |
20%緩和 |
例えば、建ぺい率40%の土地だとしても、要件を満たせば敷地面積の50~60%まで建築物を占めることが可能です。
参考元:国土交通省「建築基準法制度概要集」
容積率の基礎知識
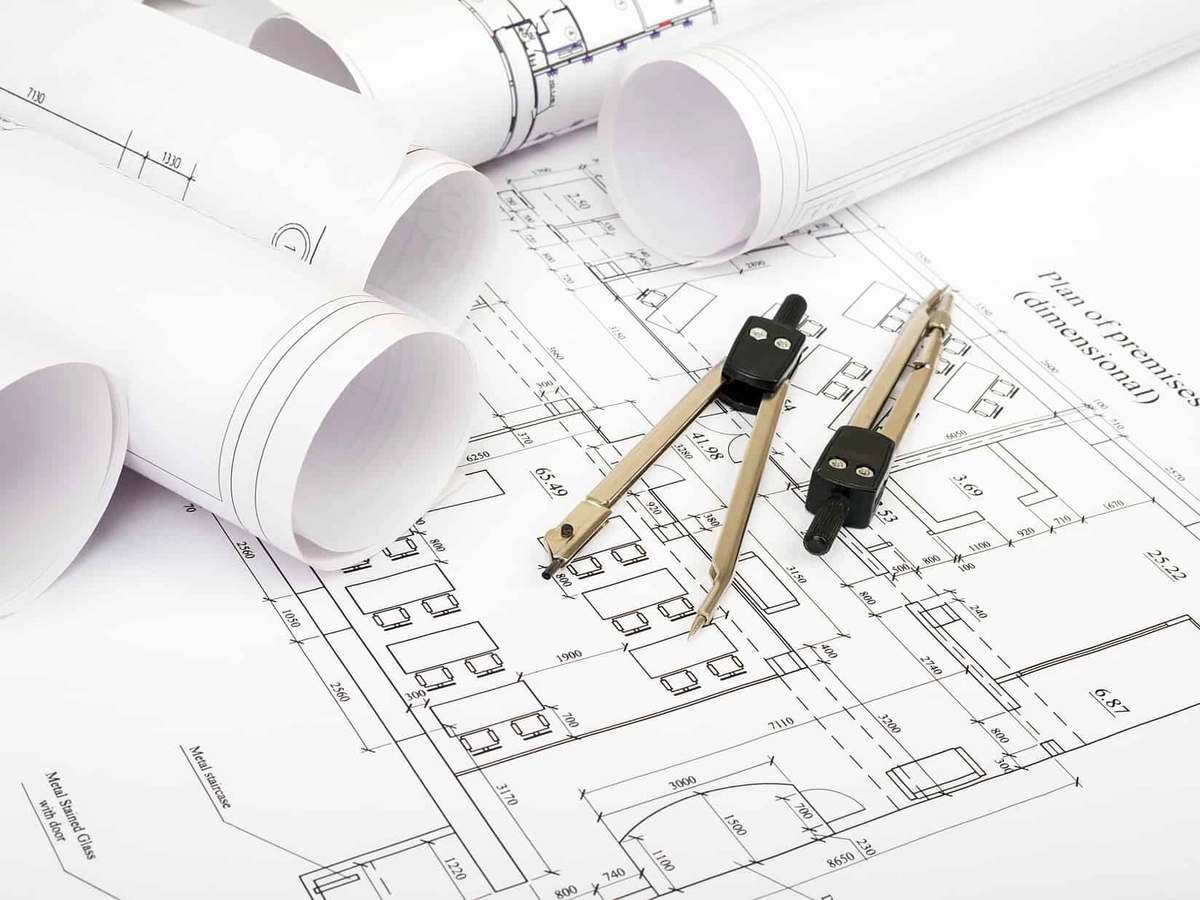 写真④住宅図面とコンパス (1).jpg 92.75 KB
写真④住宅図面とコンパス (1).jpg 92.75 KB容積率は、土地の敷地面積に占める建築物の延べ床面積の割合です。建ぺい率と違い、すべてのフロアの面積を算入するため、容積率が100%を超える土地も珍しくありません。容積率も土地ごとに設定されており、住宅の床面積の合計が範囲を超えないようにします。
容積率が設けられている理由
建ぺい率と同様に、防火対策や日当たりの確保などを目的に容積率が設けられています。そして、もうひとつの大きな理由が人口のコントロールです。
延べ床面積に制限がないと、たくさんの人が住める高層住宅が乱立する事態になりかねません。そうなると、周辺道路が渋滞したり、下水処理が間に合わなくなったりと、快適な暮らしが損なわれることも。過剰な人口増加を防いで住みやすい街にするためにも、容積率の制限が必要なのです。
延べ床面積に含まれるもの・含まれないもの
延べ床面積には、すべての階の床面積が該当します。ただし、以下の部分は含まれません。
【延べ床面積から除外される部分】
・バルコニーやベランダ
・吹き抜け
・ロフト
・玄関ポーチ など
とはいえ、すべてのバルコニーやロフトなどが延べ床面積から除外されるわけではありません。それぞれサイズや形状に基準が設けられており、条件を満たした場合に除外となります。
容積率の計算式
容積率は、次の計算式で割り出しましょう。
【延べ床面積÷敷地面積×100=容積率(%)】
土地の敷地面積が32坪、住宅の延べ床面積が40坪と仮定して計算すると、容積率は125%となります。
参考元:国土交通省「建築基準法制度概要集」
用途地域についても知っておこう
 写真⑤街の風景-min.jpg 89.81 KB
写真⑤街の風景-min.jpg 89.81 KB建ぺい率と容積率をより深く理解するには「用途地域」についても把握する必要があります。用途地域とは、自治体の都市計画に基づいてどのような建築物が建てられるかエリア分けされているもの。加えて、建ぺい率や容積率を含め、建て方のルールも決まっています。
用途地域の種類
用途地域は、13種類あります。用途地域ごとの概要やエリア内に建てられる建築物の例を一覧にまとめました。
| 種類 |
概要 |
建築物の例(住宅以外) |
| 第一種低層住居専用地域 |
低層住宅のためのエリア |
共同住宅・小中学校 |
| 第二種低層住居専用地域 |
おもに低層住宅のためのエリア |
床面積150㎡以下の店舗・学校 |
| 第一種中高層住居専用地域 |
中高層住宅のためのエリア |
床面積500㎡以下の店舗・病院 |
| 第二種中高層住居専用地域 |
おもに中高層住宅のためのエリア |
床面積1,500㎡以下の店舗・大学 |
| 第一種住居地域 |
住宅のためのエリア |
事務所・ホテル |
| 第二種住居地域 |
おもに住宅のためのエリア |
カラオケボックス・学校 |
| 準住居地域 |
道路に隣接する立地と住環境を保護するエリア |
床面積10,000㎡以下の店舗・映画館 |
| 田園住居地域 |
農業と低層住宅のためのエリア |
農産物直売所・農家レストラン |
| 近隣商業地域 |
近隣住民が買い物するためのエリア |
床面積10,000㎡超の店舗・映画館 |
| 商業地域 |
商業施設などの利便性増進を図るエリア |
百貨店・銀行 |
| 準工業地域 |
おもに軽工業の工場のためのエリア |
危険性が小さい工場・床面積10,000㎡超の店舗 |
| 工業地域 |
あらゆる工場が建てられるエリア |
危険性が大きい工場・倉庫業倉庫 |
| 工業専用地域 |
工場のためのエリア |
環境悪化リスクのある工場※住宅は不可 |
用途地域ごとの建ぺい率・容積率の制限
 写真⑥住宅街の空き地を見つめる男性-min.jpg 82.9 KB
写真⑥住宅街の空き地を見つめる男性-min.jpg 82.9 KB次に、それぞれの用途地域における建ぺい率と容積率の制限をチェックしていきましょう。
| 種類 |
建ぺい率(%) |
容積率(%) |
| 第一種低層住居専用地域 |
30・40・50・60 |
50・60・80・100・150・200 |
| 第二種低層住居専用地域 |
30・40・50・60 |
50・60・80・100・150・200 |
| 第一種中高層住居専用地域 |
30・40・50・60 |
100・150・200・300・400・500 |
| 第二種中高層住居専用地域 |
30・40・50・60 |
100・150・200・300・400・500 |
| 第一種住居地域 |
50・60・80 |
100・150・200・300・400・500 |
| 第二種住居地域 |
50・60・80 |
100・150・200・300・400・500 |
| 準住居地域 |
50・60・80 |
100・150・200・300・400・500 |
| 田園住居地域 |
30・40・50・60 |
50・60・80・100・150・200 |
| 近隣商業地域 |
60・80 |
100・150・200・300・400・500 |
| 商業地域 |
80 |
200~1,300※100%刻み |
| 準工業地域 |
50・60・80 |
100・150・200・300・400・500 |
| 工業地域 |
50・60 |
100・150・200・300・400 |
| 工業専用地域 |
30・40・50・60 |
100・150・200・300・400 |
なお、建ぺい率と容積率は、制限内の選択肢の中から最適な組み合わせに指定されています。そのため、同じ自治体・同じ用途地域だとしても、指定されている建ぺい率と容積率が異なるケースがあるのです。
参考元:国土交通省「みらいに向けたまちづくりのために」
用途地域の調べ方
用途地域を調べるには、国土交通省の「国土数値情報ダウンロードサイト」を利用してみましょう。サイトにアクセスすると、都道府県ごとの用途地域マップのデータが取得できます。また、市区町村のホームページでも、用途地域に関する情報が掲載されています。
もしくは、インターネットの検索エンジンに「調べたい地域名 用途地域」と入力して調べてみましょう。該当エリアの用途地域がリサーチできます。
参考元:国土数値情報ダウンロードサイト「国土数値情報 用途地域データ」
建ぺい率と容積率を考慮して理想のマイホームを!家づくりはR+houseネットワークの工務店へ
 写真⑦東京都_上から見たLDK (1).jpg 414.56 KB
写真⑦東京都_上から見たLDK (1).jpg 414.56 KB土地ごとに指定されている、建ぺい率と容積率。家づくりを進めるうえで、無視できません。土地探しの際には建ぺい率をはじめとする建築制限まで確認し、思い描くマイホームが実現できるか検討してみましょう。
R+houseネットワークの工務店では、建築家とタッグを組み、優れた性能とデザイン性の高さを兼ね備えた家づくりを行っています。無駄を省いてコストカットを図りつつ、お客様の理想やライフスタイルにマッチする住宅の提案が可能です。家づくりをお考えの方は、お近くのR+houseネットワークの工務店にお声がけください。
>>土地探しから家づくりのお手伝いをいたします。お気軽にR+houseネットワークの工務店へご相談ください!